〜“記憶力の低下”ではなく、“保護機能の起動”〜
1. はじめに:「名前が出てこない」が増えた…
講師の仕事でたくさんの人に会うようになった。
でも、最近特に感じる。
「あれ、この人の名前…なんだっけ?」
昔は、もっと得意だった気がする。
施設の高齢者50名を3日で覚えられたし、初対面の人の名前もスッと頭に入った。
なのに今は、何度聞いてもピンと来ない。
最初は「年のせいかな」「忙しいからかも」と思っていた。確かに、年間に100人以上の人に合う。
でも…
もしかするとこれは、「脳が自分を守ろうとしている」サインなのかもしれない。
2. 記憶力が落ちた?それとも、記憶の“優先順位”が変わった?
人の名前を覚えるって、けっこう脳にとって重たい処理だ。
なぜなら名前は、「それだけでは意味を持たない情報」だから。
→ 言い換えれば、文脈や感情と結びつかないと定着しにくい情報。
つまり、
- 自分にとって「重要」だと判断された人
- 会話や印象が「記憶」とセットになった人
でないと、脳は残す必要がないと判断している。
これは、記憶力の低下ではなく“選別”の進化だとも言える。
3. 実は、情報が“多すぎる”だけかもしれない
ケア壱のように、脳の特性で日々大量の情報にさらされている人は、
- 顔と名前
- エピソード
- 立場や役職
- プロジェクト進行状況
…など、記憶の同時並列処理がずっと続いている。
この状態で、「初対面の名前」なんて残らなくて当然だ。
むしろ脳が「もう無理。覚えなくていい」と負荷を回避してくれている。
これは、“メンタルのリミッター”が正常に働いている状態とも言える。
4. ニュータイプ脳とクロスドミナンスの記憶特性
この脳の持ち主は、
- 空気や感情を細かく拾ってしまう(右脳優位)
- 論理や文脈の処理も手放せない(左脳も同時使用)
- 手の使い方すら左右で使い分ける(クロスドミナンス)
つまり、常に“全方位で情報処理してる脳”。
名前を覚えるための余白が残っていないのは、構造的な特徴でもある。
5. 名前を“覚えやすくする”には?
「記憶しよう」と頑張るより、「記録して、使う」が正解。
✅ 名前×特徴×感情の3点セットで覚える
→「青いシャツの斎藤さん、やさしい声の人」
✅ その場で声に出して使う
→「なるほど、斎藤さんはこう考えるんですね」
✅ メモ or スマホに“出会いメモ”を残す(ケア壱のオススメ!)
→ 見返せば、その人の記憶も蘇る
つまり、インプットとアウトプットのループを意識すれば、記憶に定着しやすくなる。
6. 「思い出せない自分」を責めない
忘れてもいい。
思い出せなくてもいい。
それは脳が“安全運転”してる証。
そして、ほんとうに大切な人の名前は、きっと何度でも覚え直せる。
だから——
今のあなたの脳は、むしろ優秀です。
ちなみに、覚えた名前を忘れ始めたら・・・こちらのブログ→「Care Rebuild Project」
次回予告:
外伝 #04「人に会うと疲れる脳、でも1人すぎると不安な心」
〜“つながりたいのに、離れたい”脳のジレンマ〜
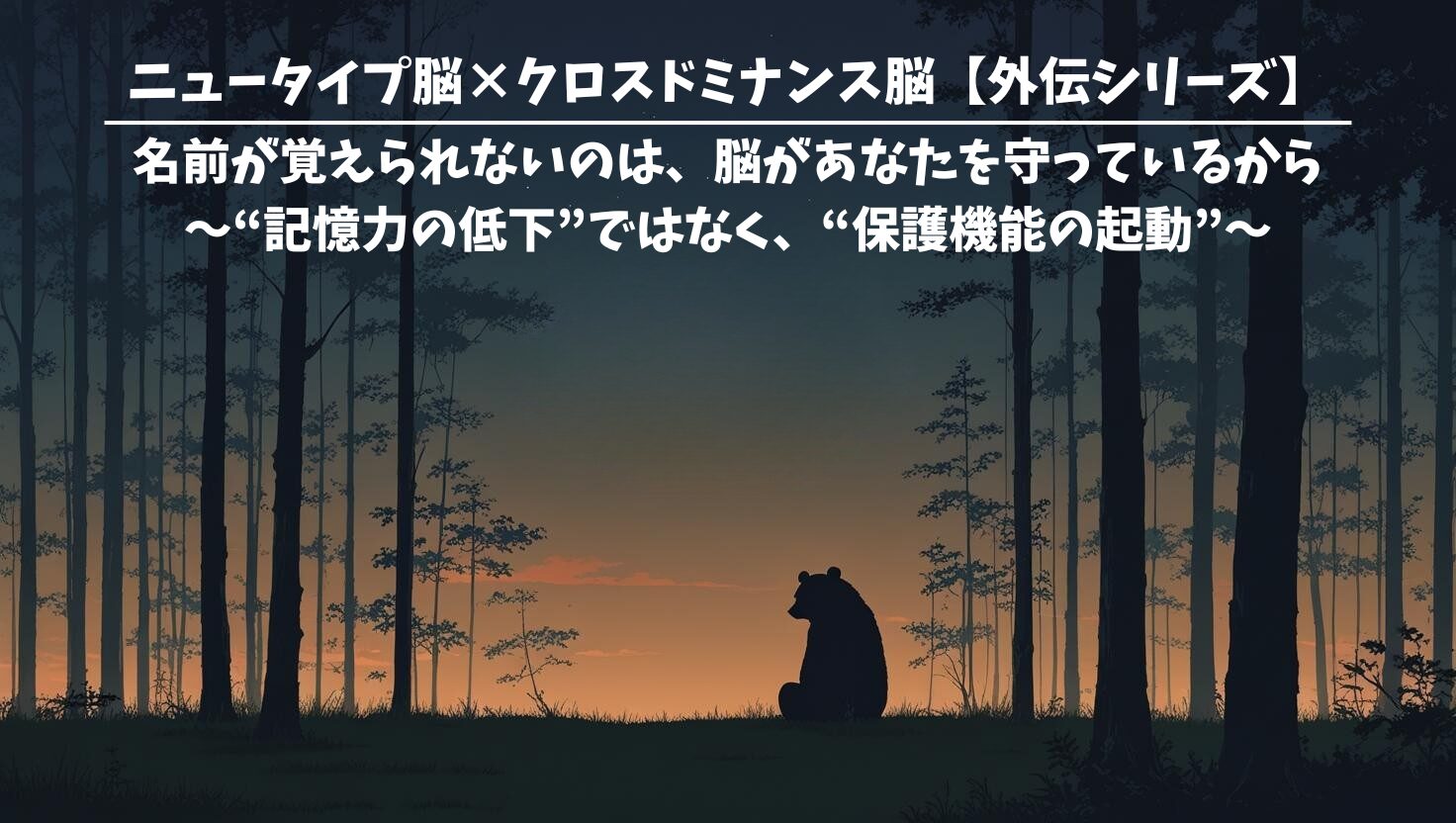


コメント