1.はじめに
「さあ、お風呂に入りましょうか」 「イヤ!今日は入らない!」
こんな会話、介護現場やご家庭で経験したことはありませんか?
高齢者、特に認知症のある方にとって、入浴は非常にハードルの高い行為です。身体の清潔を保つことは健康維持に欠かせませんが、本人が強く拒否していると、介護者としても困ってしまいますよね。
「清潔にしてあげたい」「不衛生にさせたくない」という想いで促しても、うまくいかない。怒られたり、暴言を吐かれたりして、落ち込んでしまうこともあるかもしれません。
でも、安心してください。 その「イヤ!」の奥には、ちゃんと理由があります。そして、その理由に目を向けることで、入浴拒否は少しずつ和らいでいく可能性があるのです。
この記事では、「なぜ入浴を嫌がるのか?」という背景から、日常で使える対応のヒントまでをご紹介していきます。記事の最後では、さらに視点を変えて考えるアプローチもお届けしています。日々のケアのヒントとして、ぜひ最後までお読みください。
2.背景にある気持ち
入浴拒否は、単なる「わがまま」や「反抗」ではありません。
認知症のある人にとって、浴室は異質で不安な空間。まずそのことを前提として理解することが重要です。
- 浴室の照明がまぶしすぎる
- 床が滑りそうで怖い
- 脱衣の順番が分からない
- なぜ裸になる必要があるのか分からない
- シャワーの水音がうるさくて不快
- 他人に体を見られることが恥ずかしい
こういったさまざまな感覚が複雑に絡み合って、「イヤ!」という拒否に表れているのです。
また、過去の記憶や生活習慣も影響します。銭湯文化があった世代の方であっても、介助を受けながらの入浴はまったくの別物。自分のペースでお湯に浸かれないことがストレスになる場合も。
さらに、認知症の症状として「今がいつか」「どこにいるか」が曖昧になっている方にとって、浴室という空間が「非日常」に感じられている可能性もあります。
つまり、入浴拒否の背景には、“恐怖”や“混乱”、“恥ずかしさ”など、多くの感情が入り混じっているということ。これを理解せずに、ただ「清潔にしなきゃ」と無理に入浴させようとしても、うまくいくはずがありません。
では、どうすればよいのでしょうか?
➡ このあとの「対応策」はnoteで無料公開中: https://note.com/careoji/n/n1234567890

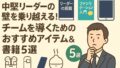

コメント